こんばんは。田中です。
この2週間、着工間もない案件が多く、主だった現場報告というのが、あまりないのですが
メンテナンス等の検討案件がいくつかあります。
まだ、対応できていない案件もあり、申し訳ありません。
その中で、コウモリが家の中に入ってくるという内容の依頼があり
私も、シロアリやネズミの対応はしたことがあるのである程度アドバイスできるのですが
コウモリの発生とその対処方については、初めてでしたので、
弊社で取引させて頂いている、阪神ターマイトラボさんにお尋ねしました。
まず、コウモリは保護動物であるということです。
ということは、殺めることは当然できないわけです。
ということは、駆除業者も存在しないということいなります。
それでは、どうすればいいか
追い出す、又は、侵入を防ぐということしかできないわけです。
いったい住宅のどんな所に潜むのでしょうか。
まず、2センチの隙間(コウモリの頭の大きさ)があれば入るそうです。
これには、正直驚きました。
コウモリを見たことがありますが、まさか2?の隙間から入れる体とは想像がつきません。
今は、建物の健全化の為、通気工法をとるので軒先などの通気口であれば2?ぐらいの隙間はあります。
換気口の隙間なども入る余地がありそうです。
まず、追い出す方法です。
コウモリは煙を嫌うそうです。
バルサンを炊いて追い出すのが一般的な方法だそうです。
ただ、7月から10月が子育て時期だそうですので
その間に追い出すと、壁の隙間で育っている雛が親を失い、壁の中で死んでしまうケースがあるそうです。
ですので、雛が巣立つ10月後半以降に対策を始めないと逆効果となるそうです。
次に、侵入を防ぐ方法
こちらは、軒や通気層廻りで隙間となっている部分をパンチングメタルのようなもので
フサグしか方法はないようです。
順番としては
家から完全に追いだして、来期に戻ってこないようフサグしかないのです。
この方法で提案させて頂き対応させていただこうと考えています。
あと、鳩除けの対応もさせて頂きました。
こちらは、八尾の現場でしたが、町中で被害にあっており、すべての家がそれぞれ
鳩除けネットを隙間に張り巡らせていました。
ネットを貼っていると、近所の方に、いくらやって『もいたちごっこよ!』と言われましたが
弊社の物件は、おかげさまで、
隙間へのネット張りを施し、寄りつかなくなったと報告を受けています。
あと、ネズミは猫を飼うのが一番効果的です。
弊社施工の私の実家でもネズミが発生しましたが
当時飼っていた猫が、追い詰め、ネズミ取り餅にひっかかって解決しました。
経験上、ネズミ取り餅を置いただけでは、ひっかかりません。
これは、私の勝手な解釈ですが・・・
ネズミの習性をつかんで必ず駆除できる方法が専門的にあると思いますので
また、その方法を習得して、お伝えできたらと思います。
お力添えできない場合もあり、誠に申し訳ありません。
BY タナカ

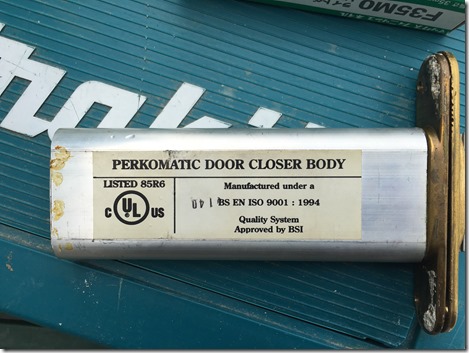











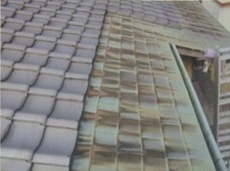




_thumb.jpg)
_thumb.jpg)
_thumb.jpg)










_thumb.jpg)

_thumb.jpg)