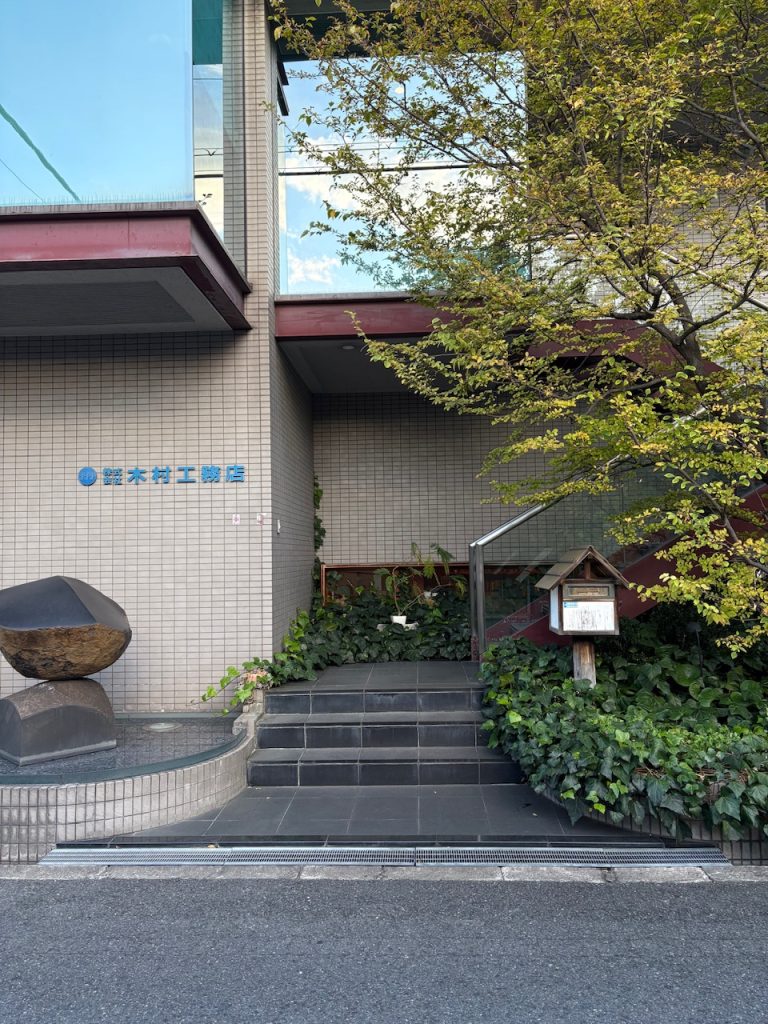竣工間近
皆さんどうも、現場監督のヒダカです。
最近寒くなってきましたね
これから本格的に冬ですね…
12月といえばクリスマスですね。
僕は今年も予定がないですが(笑)
一番下の弟からswitch2をねだられております。
手に入るとよいのですが…
さて、そんな中今日ご紹介するのは、天王寺・K様邸新築工事になります。
現場がどれくらい進んだかというと…

外部の足場が取れました!
竣工に向けてこれから外構工事の方に入っていきます。

内部も家具を付けたり、仕上げが入ったり…
着々と竣工に向けて進んでおります。
あと少し…気を引き締めて頑張ります。
それでは今日はこの辺で…
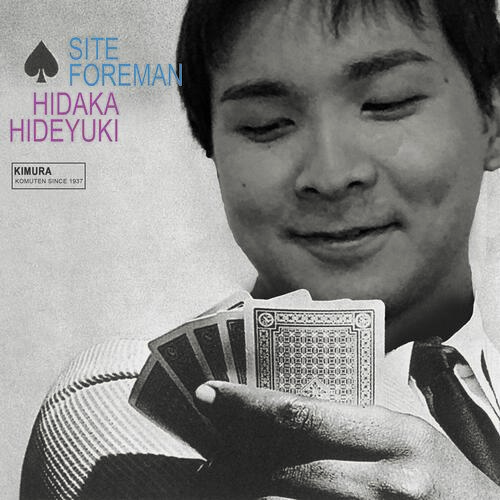
Byヒダカ