日本的感覚

建築家のウエノくんとミナミで食べて飲んで、バーに移動する途中に、インバウンドで溢れかえる心斎橋商店街を通って、うちで施工した心斎橋岩橋ビルの店舗に立ち寄った。「心斎橋筋商店街の来街者数は年間50百万人を超え本年は過去最高になる勢いです。ですが地価の上昇、それより固定資産税の上昇の勢いがそれを超えており頭が痛いです」なんていうメッセージをオーナーさんからもらった。確かに土地の価格高騰を抑える「政策」があっても良いようにおもう。土地を転がして儲かる時代じゃないほうが良さそうだし。若い世代だって、もはや簡単に土地を買えない時代になってきたし。土地公示価格の上昇が経済指標の時代なのかね。国が土地から税金を取り過ぎないほうが良い時代のような気がする。
大阪人ばかりが心斎橋筋を歩いていた時は、フツウに左側通行だったが、インバウンドで溢れ、もはやその秩序が乱れ、混沌とした状況。ぶつかるぶつかる。それがちょとオモロイ。日本国内からやってきた人が心斎橋商店街を歩いたら、周りの様子に気遣いして左側を歩くのだろうが、インバウンドの方々には、そういう気遣いの習慣が薄いのだろう。
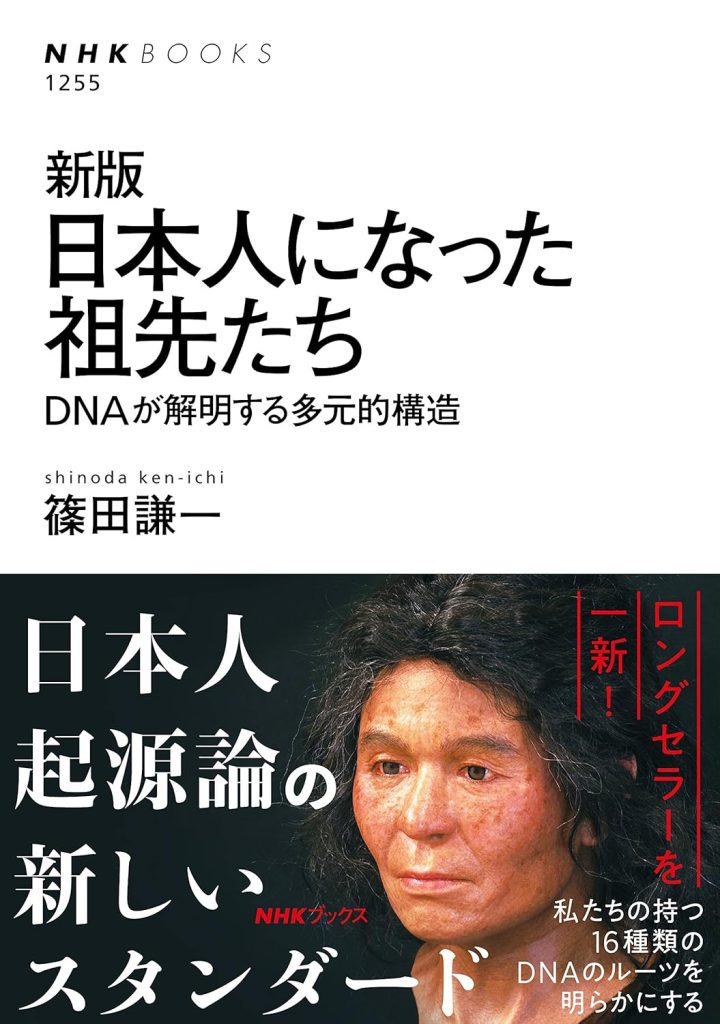
で、それが、最近、DNA分析の技術がとっても進化したらしく、ミトコンドリアDNAの女系の系譜から核DNAの男系の系譜までたどれるようになって、そういう事を分かり易く解説してくれはる国立科学博物館の館長の篠田謙一さんの話や著作が面白い。縄文時代とか弥生時代の人種のありようがDNA分析によって明確になってきているそうだ。縄文から弥生そして古墳時代には多くの人種が日本にやってきて、混ざって、いまの日本人ができているという。心斎橋歩きながら「DNAが解明する多元的構造」をおもいだして、さて、これから、インバウンドの方々との共生がどのように展開していくのだろうか….なんておもった。
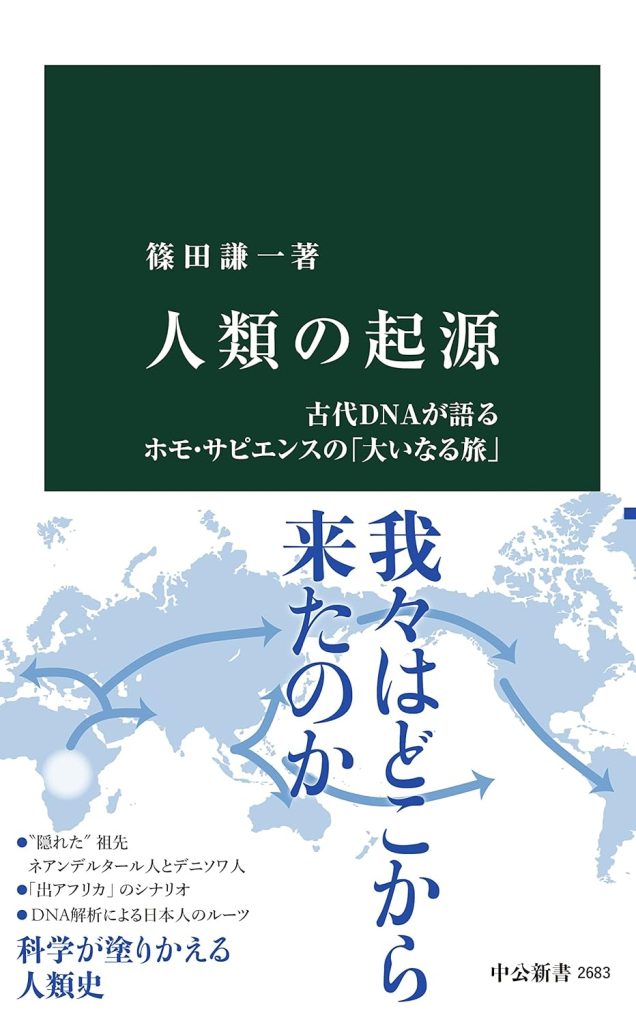
「こもれ日」とか「水面の光のゆらぎ」とか、そういうコトバは日本独特の表現らしい。同じような自然現象に同じ美つくしさを世界の多くのひとが感じるのだろうが、それを表す「ことば」や「美意識」に日本の独特の感覚があるらしい。「儚さ」「静けさ」「移ろい」という感情の余韻から「侘び寂び」「物の哀れ」の美意識につながっていくのだろう。で、朝、自転車に乗ると、そういう景色に出くわし、そういう感覚が忍び寄ってくるのが、ちょっとした楽しみ。

↑ 朝護孫子寺の参道を歩くと、時として、朝の木漏れ日に出会う。

↑ 信貴山に吊り橋があって、誰もいない吊り橋の真ん中に立って、池の水面を眺めると、水のゆらぎが、気持ちエエ。

↑ 柏原の葡萄畑から大和を眺めると、葡萄の養生シートに朝日があたり、風ふいて、その光のきらめきが気持ち良い。

そうそう、7月31日と8月1日に地元の清見原神社の夏祭りがあって、4台の地車が、会社の前を通過する。ご祝儀を渡し一緒に大阪締めをするのが楽しみ。気を使って「木村工務店の商売繁盛を祈願して…..」なんて口上を述べてくれる。にしても、今年は暑すぎて暑すぎて、子供たちが綱を引くのが少ない感じだし、元気な地車ギャルの姿も少ないし。地車が通過しても家から道路に出て邪気を払ってもらう人もほぼいない。そんななかで、地車を運行する皆さん、ほんと、ご苦労さまでした。
そんなこんなで、選挙もあって、なんとなく「日本」を「感覚」してみた週だった。
