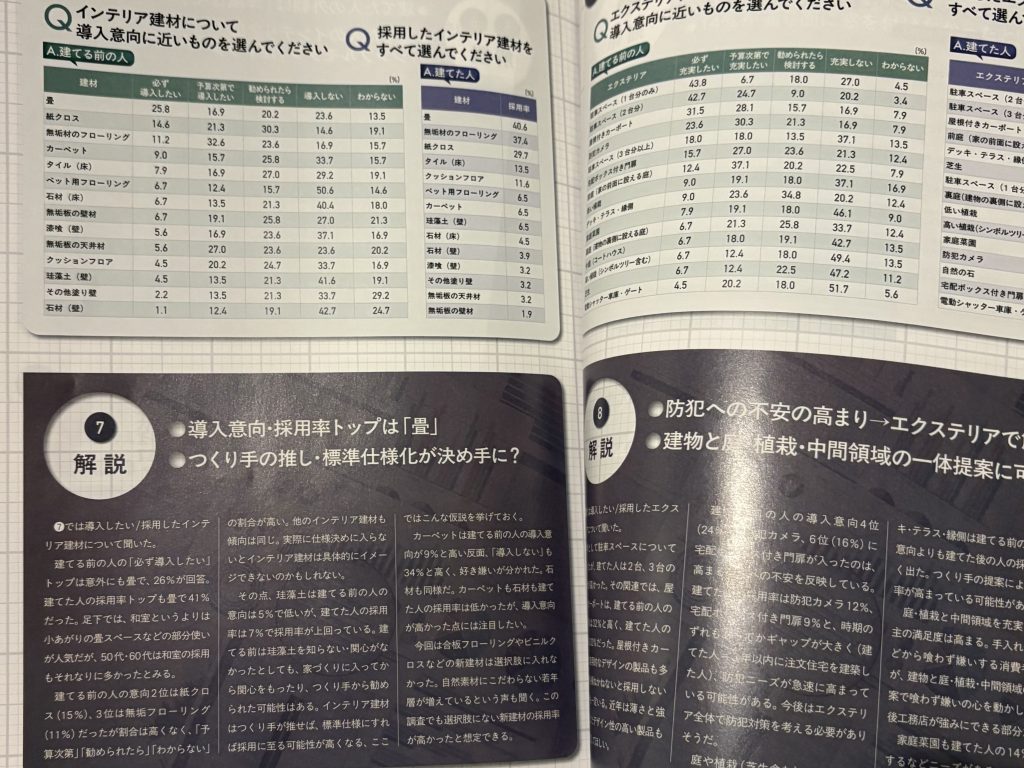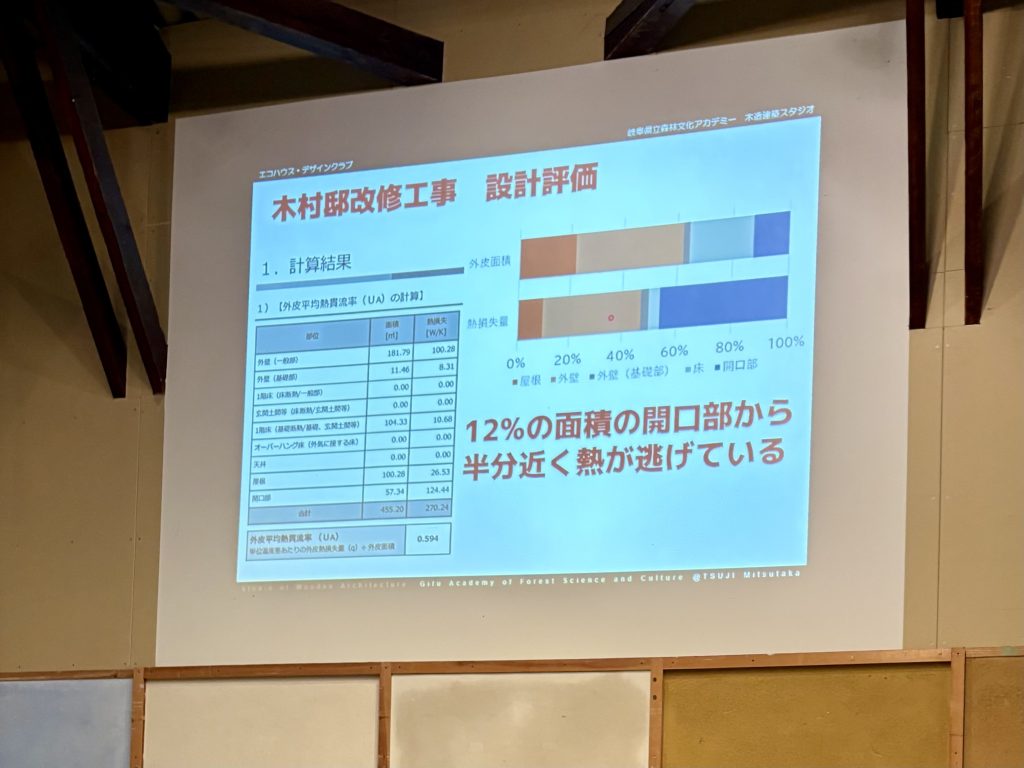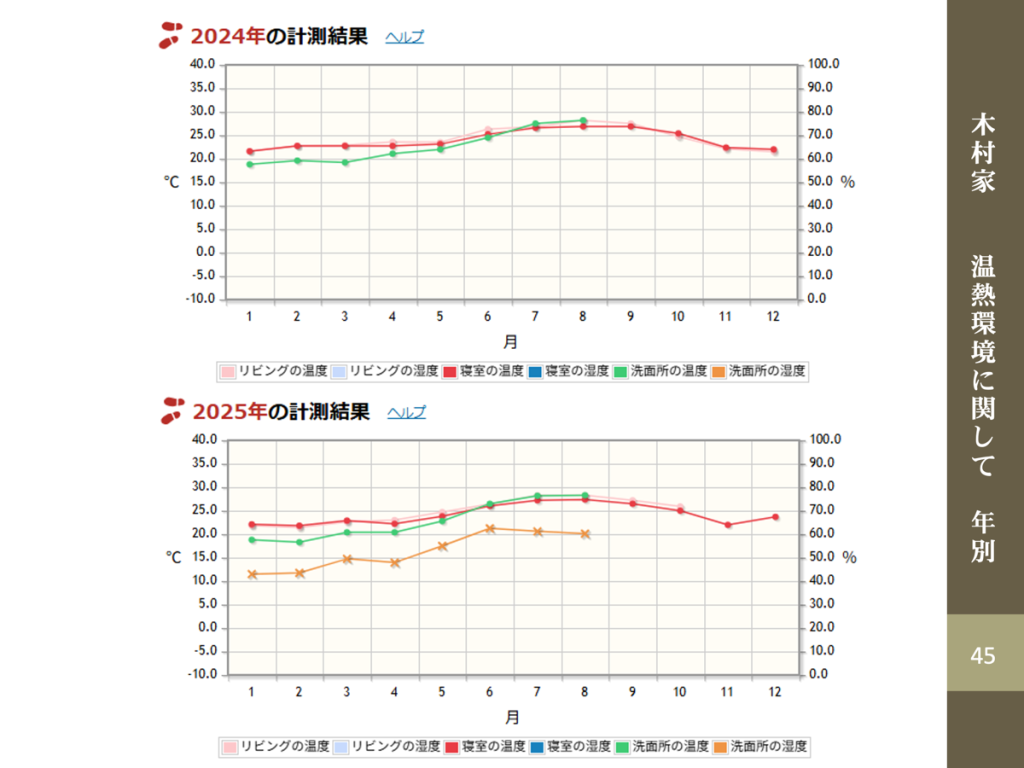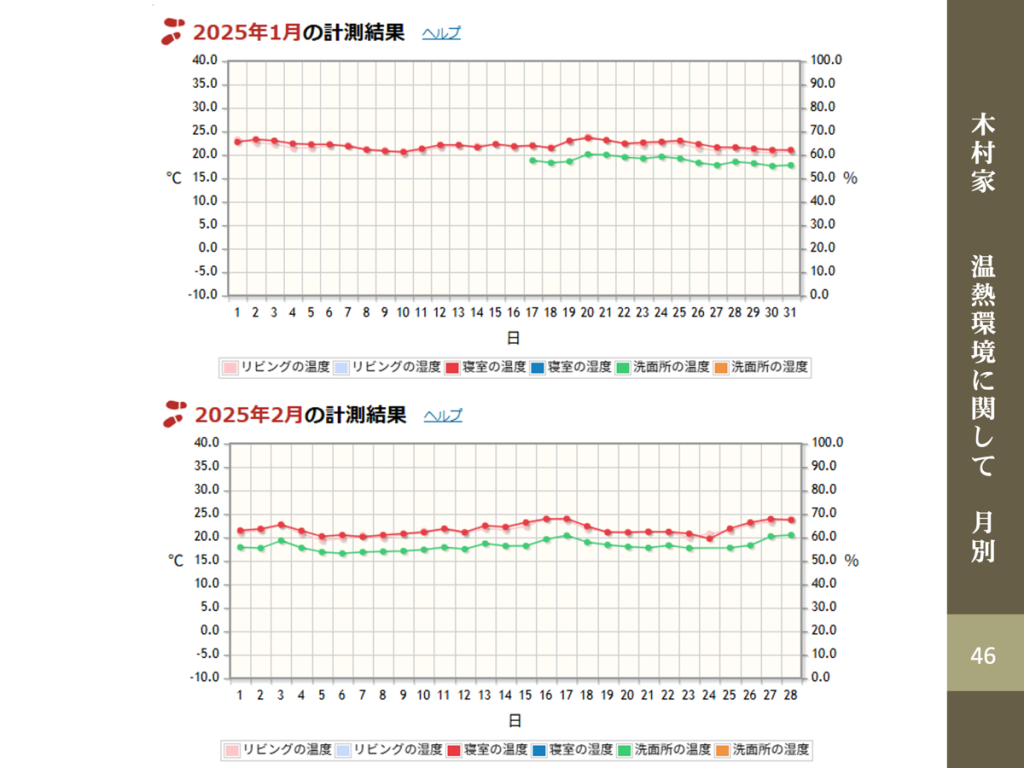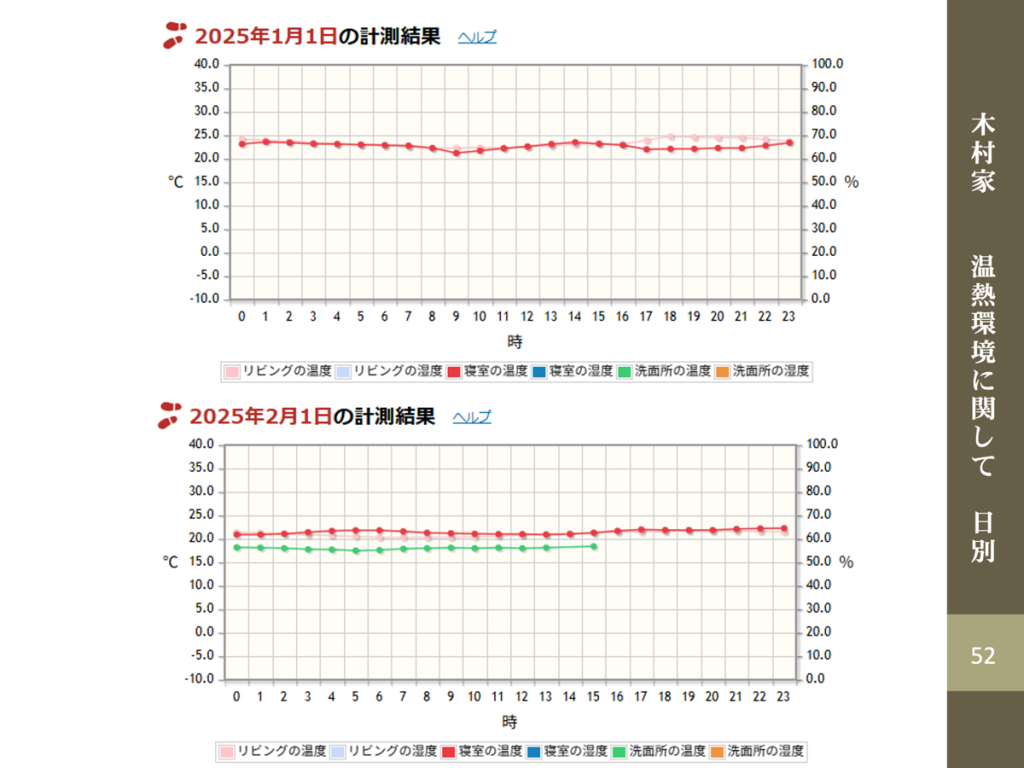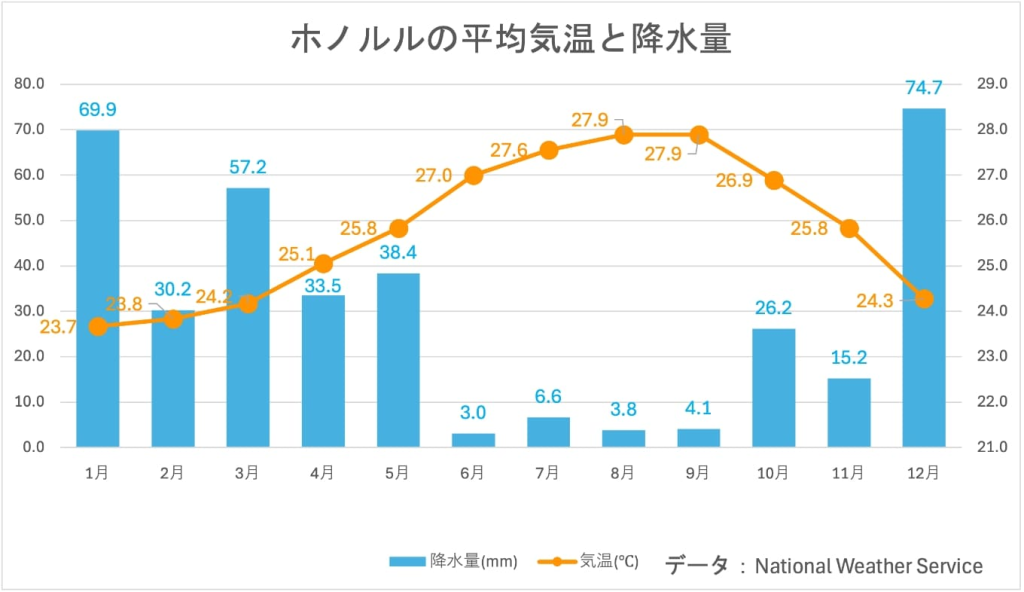3分間の出来事
新年会が月曜日から金曜日まで連続した週。生野区の会合に出席するために、地下鉄に向かい、プラットフォームの4席の椅子の一番左端に座る。電車が来るまで3分ほど。携帯でも眺めながらひと息ついていると、階段から降りてきた高校生の男子3人が、プラットホームを歩き、私の前を通り過ぎて、空いている椅子3脚に、順番に座る。
座るなり、ひとりの男子が、「高市どぉおもう…..」と二人の男子に聞く。ほんの少しの間があって「消えるんとちゃぅか…..」とひとりが答える。そうするともうひとりが、「ちょっと、はしゃぎすぎやなぁっ」という。おもわず笑みがこぼれてきそうやったけど、ぐっと無表情にした。最初に話を振った男子が、「中道に吸収されるのとちゃう…..」と答えた。ちょうどその時に、電車がプラットホームに到着します…..というアナウンスがあって、4人が同時に椅子から立ち上がり、電車に乗り込む準備をして、会話はここで終わる。
かつて高校生が、こんなふうに政治を語っている場面に遭遇したことがない。好き嫌いやキャラだけではなく、「消えるか」「吸収されるか」「はしゃぎすぎか」。言葉は素朴だが、政局とか、ポジションとか、持続性とか、構造で政治を語る雰囲気がエエねっ。3人とも18歳で選挙権あるのかどうか…..。
そうそう大学の建築学科の課題発表の後に、懇親会があって、4人ほどの21歳女子に「高市さんどぉおもうの…..」と聞いたら、全員が、応援してます!投票に行きます!と好意的だった。若い人の投票率が過去最高だったら面白いねっ。SNSで政治が日常会話に入り、不安(将来・経済・戦争・気候)がリアルで「選ばないこと」がリスクだと感じ始めているからなのだろうか…..。若者は政治に無関心ではなく、自分達のコトバで語れる時代になってきているのかも。

「MMM−1グランプリ」といって、昨年末のM1を完コピして、演じる遊びがあるらしい…..。その主催者である紙芝居屋のガンちゃんが、木村工務店の加工場で開催できますか…..ということになって、今日の1月25日日曜日の午後2時から開催された。男女関係なく、くじで当たった人とコンビを組んで、くじで割り振られたM1漫才のネタを、真剣に演じる。そんなので笑えるのか…..とおもったら、案外笑える。大笑いと言うより微笑ましい笑いでもあって。オモロイ。
「笑い」って何なのかっとおもう。ネタが、しっかりして、M1の決勝に残り笑えるネタなら、素人が真剣に取り組んでも、ある程度、笑えるのだなっ。審査員3人が点数を付け、残った上位3人から、お客さんの投票によって、優勝者を決める方式で、「エバース」を演じたグループが優勝した。ネタが飛んだ時の間が良かって、そんなのも評価された。実際のM1優勝者は「たくろう」だったが。二人の相方のキャラを真似るのが、最も難しかったのが、たくろうのように感じた。特に赤木さんのキャラは唯一無二のキャラと間だなっと、改めて知った。一生懸命では演じられないキャラと間なんだろう。プロとはそういうものかもしれない。
漫才も3分間ほどだし、3分間の出来事に刺激を受けた今週だった。